最近、米国スターバックスが「数百店舗閉鎖」などのニュースで揺れている。一方、日本のスターバックスは売上・利益ともに過去最高を更新している。なぜ同じブランドでありながら、本国アメリカでは苦戦し、日本では順調なのか。その違いを見つめることで、国ごとの消費文化や価値観が浮かび上がってくる。
2025年9月の店舗閉鎖の話題

2025年9月、スターバックスは北米で数百店舗を閉鎖すると発表し、世間を驚かせた。対象となるのは主に大都市圏の店舗や、売上の伸び悩む郊外の拠点である。閉店の規模は数百店舗規模に及び、全体のネットワークを見直す大きな決断となった。閉店の理由には、インフレによる消費の冷え込みや人件費・賃料の高騰、そして競合激化による収益性の低下がある。
ただし、閉鎖は単なる撤退ではなく、戦略的な再編の一環とされている。閉店後の一部の店舗はリロケーションされ、より需要の高いエリアやドライブスルー需要が強い場所へ再出店する計画がある。また、残された店舗には最新のオペレーション技術やデジタル機能が重点的に導入される見込みだ。つまり「縮小」ではなく「再配置」を通じて、効率的で利益率の高い体制を築くことを目指しているのである。
- 対象店舗:大都市圏の一部や収益性が低い郊外店。
- 閉鎖規模:北米全体で数百店舗規模。
- 閉店理由:消費の冷え込み、人件費・賃料上昇、競合の激化。
- 閉店後の方針:需要の強い地域へのリロケーション、残存店舗への技術投資強化。
1. 米国スターバックスコーヒーが不調な理由
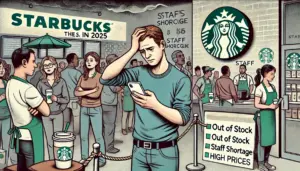
アメリカのスターバックスを訪れると、店内の空気がどこか急ぎ足だ。かつては小さな贅沢として胸を満たした一杯が、今では節約対象に数えられてしまう。注文の列に並んだ人々は、スマートフォンを握りしめ、待ち時間の長さに苛立ちを募らせる。そこにあるのは、ブランドが抱えてきた誇りではなく、時代の重みだ。過去の輝きは、人件費や物価の上昇にかき消され、日常に溶け込み過ぎたがゆえに特別感を失ってしまったように映る。
- インフレと節約志向:高インフレと金利高止まりで、消費者は毎日の数ドルを節約しがちになった。スタバは「削れる贅沢」の対象に。
- コスト上昇:人件費、賃貸料、物流、原材料の高騰が利益を圧迫。
- 労働組合問題:全米で労組活動が拡大し、交渉やストによる運営負担が増大。
- 待ち時間の不満:カスタマイズ注文やモバイルオーダーの集中、スタッフ不足により「遅い」との声が増加。
- ブランドの日常化:かつて特別だった体験が日常に埋もれ、魅力が薄れた。
2.日本スターバックスコーヒーが好調な理由

日本のスターバックスに足を踏み入れると、そこは喧騒から切り取られた小さな舞台のようだ。桜の時期には淡いピンク色のラテが登場し、SNSに映える一瞬を生む。学生がノートを広げ、ビジネスパーソンが資料を開き、友人同士が会話を重ねる。誰もがその空間に「居場所」を見いだしている。特別なドリンクがきっかけとなり、アプリのポイントが理由となり、そしてカウンター越しの笑顔が、それらを確かな体験へと昇華させる。日本ではスタバは単なるカフェではなく、日常と非日常の境界線を軽やかに越える場として息づいている。
- ブランドの特別感:日本では「ちょっとした贅沢」として支持を維持。非日常的な体験価値が強い。
- 限定メニュー戦略:桜ラテなど季節・地域限定商品がSNSで話題化し、来店動機を生む。
- サードプレイス文化:家や職場以外の「第三の居場所」として利用が定着。学習や仕事の場にも。
- デジタル活用:アプリやリワードプログラムがリピーターを確保し、売上に貢献。
- 安定した運営環境:米国ほど人件費高騰や労組問題が深刻ではなく、比較的スムーズな経営が可能。
3.米国スターバックスが「遅い」といわれる背景

アメリカのスターバックスに対する顧客の不満の中で、特に目立つのが「提供が遅い」という声である。その背景にはいくつかの要因が重なっている。まず、注文の複雑化がある。カスタマイズの自由度が非常に高いため、1杯ごとの作業工程が増え、調理時間が延びてしまう。また、モバイルオーダーが普及した結果、ピーク時にはアプリからの注文と店頭注文が同時に殺到し、処理能力を超える混雑が起こる。さらに、労働コストの上昇と人材不足により、必要な人員を確保できない店舗も少なくない。ドライブスルー併設店では、店内と車列の対応を同時に行うため、遅延が顕著になることもある。
こうした事情から、米メディアやSNSでは「コーヒー1杯に10分以上待たされる」「出勤前に寄れなくなった」といった声が広がった。アメリカでは“スピード”が求められるがゆえに、待ち時間は顧客満足度に直結する。結果として「遅いスタバ」というイメージが定着し、競合他社へ顧客が流れる一因となっている。
- 注文の複雑化:多様なカスタマイズが調理時間を長引かせる。
- モバイルオーダー集中:ピーク時にアプリ注文と店頭注文が重なり混雑。
- 人員不足:労働コスト上昇と人材難により十分なスタッフが確保できない。
- ドライブスルーの負担:車列と店内対応が同時進行し、処理能力を圧迫。
- 顧客の不満拡大:SNSや報道で「遅い」との印象が広まり、ブランドへの影響に。
4. 改善に挑む米国スターバックスコーヒー
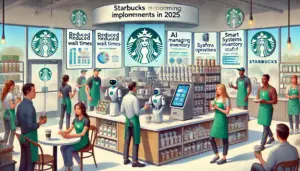
アメリカのスターバックスも黙っているわけではない。新しい技術の導入で待ち時間を削り、AIが在庫を見張る。しかし、改善の影で現場のスタッフが抱える重荷は増しているという声もある。改革の兆しは見えているが、それが全土に根を張るには時間が必要だ。焦りと希望が同居する状況の中で、アメリカのスターバックスは新しい解決策を模索し続けている。
- 技術導入:一部店舗で平均提供時間を2分短縮する成果。ピーク時の完成率向上も。
- AI活用:在庫管理やスタッフ配置を効率化し、オペレーション改善を図る。
- 現場の声:一方で「負担が増した」という従業員の声もあり、全国的改善は道半ば。
改善に対する課題と懐疑的な見方・リスク
改善策が導入されても、それが全ての店舗で効果を発揮するとは限らない。都市部と地方では客層も需要も異なり、画一的なシステムではむしろ柔軟性を欠く恐れがある。また、AIや自動化による効率化は、従業員に「監視されている」という圧力を与えることもある。さらに、技術投資が増えることでコスト負担が膨らみ、長期的に採算が合うのかという懐疑も残る。顧客が求めるのは速さだけではなく、人と人との温かい交流であるはずだ。効率化が進むほどに、その大切な体験が犠牲になるリスクが存在している。
- 地域差の問題:都市部と地方で事情が異なり、一律の改革は難しい。
- 従業員の負担増:AI導入が監視感を強め、働きやすさを損なう可能性。
- コストの懸念:巨額の技術投資が長期的に回収できるか不透明。
- 顧客体験のリスク:効率化が進むことで、人間的な交流が失われる恐れ。
5.スターバックスコーヒージャパンの新たな挑戦
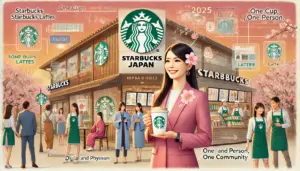
2025年、日本のスターバックスは新しいページを開いた。森井久恵氏のCEO就任である。彼女は日本人女性として初めてスターバックスジャパンのCEOに立ち、話題を集めた。国際基督教大学を卒業後、NTT東日本やユニリーバ、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンなど多様な企業で経験を重ね、2018年にスターバックスへ。CMOとしてマーケティング戦略を担い、やがてCRMOとして店舗運営とマーケティングの両輪を統括した。
彼女の発言には常に「人」が中心にある。コロナ禍では“自分の子どもを店舗に立たせられるか”を問いとし、従業員を守る判断を下したという。顧客体験と同時にパートナー体験(従業員体験)を重視し、その二つを結びつけることでブランドの力を高めてきた。森井氏のビジョンは、単に売上を伸ばすことではない。彼女が掲げる「一杯、一人、一地域を大切に」という言葉は、店舗を通じて人と人、人と地域を結ぶ姿勢を映している。
限定商品を通じた驚きやワクワク感、地域ごとの文化との融合、デジタルとリアルの統合。それらを駆使して、スターバックスを「ただのカフェ」から「記憶に残る体験の場」へと進化させようとしている。彼女の就任は、スターバックスジャパンが次の成長段階へ進む合図であり、多様性の象徴としても意味を持つ。ブランドを未来へ導く力は、数字の先にある“体験の質”を見据える眼差しに支えられている。
- 森井久恵氏のCEO就任:2025年、日本人女性初のCEOとして森井氏が就任。「一杯、一人、一地域を大切に」という理念を掲げる。
- 地域と文化の融合:地域ごとの特色を大切にしながらブランドを深化させ、30周年を見据えた新しい方向性へ。
森井久恵氏のプロフィール(まとめ)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 基本情報・略歴 | 滋賀県出身(報道による推定)。国際基督教大学卒。NTT東日本、ユニリーバ、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンを経て2018年スターバックス入社。CMO、CRMOを歴任し2025年CEO就任。 |
| 特徴・信条・スタイル | 「人」を中心に置いた判断。コロナ禍では従業員を守る方針を貫き、顧客体験と従業員体験を結びつける経営スタイルを展開。 |
| 意義・期待される役割 | 日本人女性初のCEOとして多様性を象徴。地域文化と融合し、体験価値を高めながら次の成長段階へ導くリーダーとして期待されている。 |
まとめ:米国スタバ不調、日本スタバ好調。何が違う?
アメリカでは「日常化とコスト圧力」が逆風となり、日本では「特別感とブランド戦略」が追い風となっている。スターバックスという同じ看板を掲げていても、国によって求められる役割は異なる。その差異は単なる経営の比較にとどまらず、人々が日々の暮らしの中で何を大切にしているのかを映す鏡でもある。
コーヒーを飲むという行為の奥には、それぞれの国の呼吸のようなものが潜んでいる。アメリカでは速さを求め、日本では物語を求める。その違いが、不調と好調の分岐点を生み出しているのだろう。
- アメリカでは消費者が節約志向を強めている
- インフレと物価上昇が日常のコーヒー需要を冷やしている
- 労働組合の拡大が経営の柔軟性を制限している
- 提供の遅さが顧客満足度を低下させている
- ブランドが日常化し特別感を失っている
- 日本では桜ラテなどの限定商品が強い集客力を持っている
- 日本の消費者にとってはスタバは「ちょっとした贅沢」
- アプリとリワードでリピーターが確保されている
- 日本の店舗はサードプレイスとして根付いている
- 米国では技術改善が進むが課題も多い
- 改善が従業員負担やコスト増につながるリスクがある
- 米国では再編のために数百店舗の閉鎖が行われた
- 閉店後も需要の高い地域へのリロケーションが進められる
- 日本では森井久恵CEOが「一杯、一人、一地域」を掲げる
- 今後は国ごとの文化や消費者心理に合わせた戦略が鍵となる

 参照:
参照:
